社労士コラム
~多忙な時期にサッと把握!命取りとならないための36協定締結を教えます~
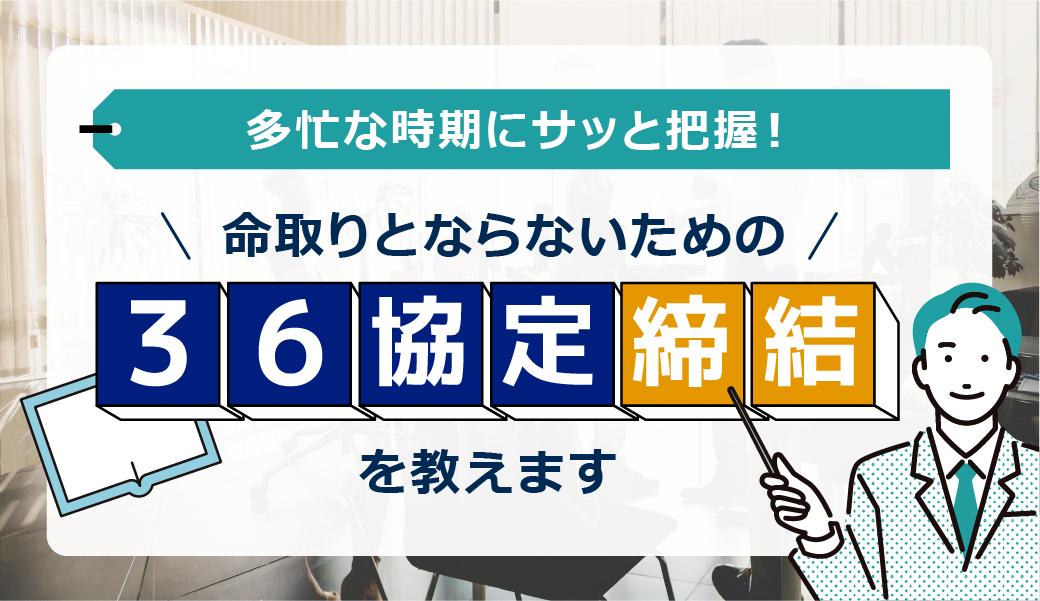
- 監修者
- 社会保険労務士法人ヒューマンリソースマネージメント
特定社会保険労務士 馬場 栄
3,500社を超える企業の就業規則改定を行ってきた実績を持つ。
また、豊富な経験と最新の裁判傾向を踏まえた労務相談には定評があり、クラウド勤怠のイロハから給与計算実務までを踏まえたDX支援を得意としている。
https://www.human-rm.or.jp
目次
①法定外残業、休日労働がなければ36協定の締結をしなくてもいい!?
労働基準法では1日8時間、週40時間が労働時間の上限と定められており、これを超える労働は認められていません。
この労働時間の上限を超えて労働させる場合には、36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)を労使で締結し、労働基準監督署に届出する必要があります。
一方で、休日労働させる場合も36協定が必要となります。なお、ここでいう休日労働とは、法定休日(週に1日または4週間を通じて4日与える義務のある休日)のことです。
1日8時間や週40時間以内で労働させることができる場合や週に1回必ず休日が取れる場合は締結しなくても問題ありませんが、36協定を届出せずに法定外残業や休日労働をさせた場合、労働基準法違反となります。
労働者が予定時間より早く出勤して仕事をしているケース、定時後に隠れて業務をしているケースなど、思わぬ形で労働時間と認定されることがあります。勤怠を労使で確認することも重要ですが、思わぬ形で労働基準法違反となる可能性もあるため、36協定の締結および届出を行っておくとよいでしょう。
②一般条項の36協定と特別条項付き36協定の違い
36協定には「一般条項の36協定」と「特別条項付き36協定」があります。
「一般条項の36協定」で延長が認められている時間は、1か月45時間、1年360時間が上限です。 しかし、繁忙期に上限時間を超えて労働せざるをえない場合もあるでしょう。そのような事態に対応するため、「特別条項付き36協定」を締結することで、「一般条項の36協定」の時間を延長することが認められています。
「特別条項付き36協定」の上限は、下記のとおりとなります。
- ・年間720時間以内(時間外労働のみ)
- ・単月100時間未満(時間外および休日労働時間の合計)
- ・2か月から6か月の複数月平均で80時間以内(時間外および休日労働の合計)
特別な事情がある場合でも、これらの時間を上回ることは認められていません。
また、「一般条項の36協定」の上限である月45時間を超えられる回数は年6回(1年のうち6か月)までとされています。
特別条項を設ける場合には、以下の事項について定め、記載する必要があります。
- ・限度時間を超えて労働させることができる場合(業務上の都合などの表記は不可)
- ・限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康および福祉を確保するための措置
- ・限度時間を超えた労働に対する割増賃金の率
- ・限度時間を超えて労働させる場合の手続き
例えば、残業が月40時間になることがある、突発的なクレームやシステムダウンなどに対応する可能性がある場合、上限時間を超えて働く可能性もあるため、「特別条項付き36協定」を締結しておくのがよいかもしれません。
③36協定の作成~届出までの流れで押さえておくべき点
ここからは、36協定を届出するまでの流れと押さえておくべき点を解説します。
36協定を届出するまでのおおまかな流れは以下のとおりです。
- ● 1日・1か月・1年の延長時間を定める
- ● 休日労働の回数と時間を定める
- ● 有効期間と起算日を定める
- ● 労働組合の代表または労働者の過半数代表を選出する
- ● 労働者の過半数代表者と会社の代表者で36協定を締結する
- ● 管轄する労働基準監督署へ届出する
(1)1日・1か月・1年の延長時間を定める
36協定は「1日・1か月・1年」単位で、それぞれの延長時間を定める必要があります。
延長時間を定める場合には前述の一般条項の範囲で収まるか特別条項を発動する可能性があるかを検討しましょう。
なお、36協定で定める延長時間は、法定労働時間を超えた時間です。所定労働時間を法定労働時間未満で就業規則に規定している場合には、法定労働時間を基準に検討しましょう。例えば1日の所定労働時間が7時間30分と規定している場合が該当します。
(2)休日労働の回数と時間を定める
休日労働には法定休日(週1回の休日)に労働する回数と時間を定めます。
週休2日制としている会社では、所定休日と法定休日で構成されていますので、法定休日を基準に検討しましょう。法定休日を就業規則で定めていない場合には、1週間で区切ったうちの後順位の休日を法定休日として考えます。
(3)有効期間と起算日を定める
有効期間とは、36協定が適用される期間のことをいいます。
定期的に見直しを行う必要があると考えられることから、1年とするのが原則です。
一方、起算日とは、36協定で定めた1年間の延長時間のカウントをはじめる日を指しています。
そのため、起算日は賃金計算期間に合わせると運用しやすくなります。たとえば、給与の締日が末締めの場合は「〇年4月1日」、20日締めの場合「〇年3月21日」などです。
勤怠の集計は賃金計算期間ごとに行うため、起算日と賃金計算期間がずれていると実労働時間を集計するときに煩雑となります。
特別な事情がない限り、起算日と賃金計算期間は合わせるとよいでしょう。
(4)労働組合の代表または労働者の過半数代表を選出する
36協定の締結の際には、労働組合の代表または労働者の過半数代表を選出し、36協定届出書にその代表者の選出方法を記入する必要があります。
過半数代表者には、労働基準法第41条に該当する管理監督者を選任することはできません。肩書がない者が従業員代表として選出された場合でも、実質的に「経営者と一体的な立場」であると判断された場合には、締結した36協定も無効となります。
過半数代表者の選出方法は、投票や挙手による選出が一般的ですが、社員親睦会の代表を自動的に過半数代表としたり、使用者が指名したりする選出方法は認められていません。このような方法で選出された過半数代表者により締結された36協定は無効となります。
この選出方法について当法人では、Googleフォームによる投票をお勧めしています。
理由としては、導入しやすく使い勝手がよい、回答結果の集計が簡単に確認できる、スプレッドシートに連携することでエビデンスとして残すことができるためです。
(5)労働者の過半数代表者と会社で36協定を締結する
36協定を締結する際は、会社側の代表と労働者の過半数代表者が合意した証明が必要です。2021年4月から原則、押印廃止となりましたが、押印不要となる条件は、労使協定と36協定届を分けて作成した場合に限ります。
そのため、36協定届が労使協定を兼ねている場合は、署名または記名押印が必要となります。
協定を締結する際に労働者代表が記名押印をしない場合には、当然ながら36協定は成立せず、法定外残業をさせることができなくなります。そのような事態を避けるためにも、会社から丁寧な説明をし、しっかり理解をしてもらうように努めることが大切です。
(6)管轄する労働基準監督署へ届出する
締結した36協定は、「協定の成立年月日」を記入してから労働基準監督署に届出する必要があります。
「協定の成立年月日」は、36協定の届出年月日より前の日付としなければ、労働基準監督署で受け付けてもらえません。届出する前に必ず確認しましょう。
労働基準監督署に届出する方法は、直接労働基準監督署の窓口に提出する方法のほか、郵送と電子申請の3つの方法があります。なお、窓口や郵送で提出する場合は、36協定届のコピーを同封して、控えをもらうのが一般的です。
④うっかりでは済まされない注意点!?
(1)更新が遅れ、前36協定の有効期限が過ぎたあとに新36協定を提出した場合
更新が遅れ、前36協定の有効期限が過ぎたあとに新36協定を提出した場合、届出をした日から効力が発生します。
たとえば、4月1日に有効期限が切れているにも関わらず4月5日に届出した場合は、4月1日から4月4日は、36協定が適用されません。
届出が遅れて有効期限が切れている期間に法定外残業をさせた場合は、労働基準法違反となるため、36協定の更新は有効期限が切れる前に届出する必要があります。
(2)届出すれば完了ではない!?
36協定は届出後に、従業員へ周知することが義務となっています。周知がされていない場合には有効となりません。
周知の方法は、会社内で従業員の方がよく目にする箇所への掲示(休憩室、更衣室など)がありますが、景色と化してしまい従業員がきちんと認識できないケースがあります。届出が完了した後には、全社ミーティングで36協定の意味、上限時間などを説明する時間を設けることをお勧めします。
(3)36協定の締結は一括でできない
36協定の届出は、本社と各事業場の就業規則の内容が同一であることや、電子申請で届出するなど、要件を満たせば一括で届出が可能です。しかし、協定の「締結」は事業場ごとに行わなければなりません。
たとえば、東京本社と大阪支店がある会社では、それぞれの事業場で36協定を締結してから東京本社で一括で届出することになります。
36協定の手続きはうっかりとしたミスが命取りとなりますので、手続きの流れは確実に押さえておきましょう。
⑤36協定締結で改めて考えたい「残業時間」について
36協定の届出は、従業員を労働基準法で定められている上限時間を超えた労働を可能とするための重要な労使協定です。
36協定締結により労働者に働いてもらえる時間の枠が広がりますが、上限時間は、あくまでも例外的に働くことを想定しています。長時間労働は、労働者の心身や私生活に影響が出ますので、少しでも残業時間を減らしていく必要があります。
残業時間が多い、または偏っている場合には、
- ・ワークシェアリングにより業務分配を行う
- ・社内手続きを始めとした事務作業が煩雑であれば、システムを入れて効率化を図る
- ・新規案件を受注する際には現場の労働力や作業時間を加味して受注を調整する
といった形で残業時間を減らす仕組みを構築していくとよいでしょう。
長時間労働は近年採用および離職にも大きく影響しています。少子高齢化により人材不足が加速しているため、「残業時間」を減らす取り組みは今後も求められるでしょう。
セコムトラストシステムズからのご紹介
最後に、セコムトラストシステムズから時間外労働を管理するうえで便利な「セコムあんしん勤怠管理サービス KING OF TIME Edition」の機能をご紹介します。
《36協定(一般条項、特別条項)締結時間の管理方法について》
36協定の届出に記載された上限時間(回数)や、上限に達する前に警告を行うための警告時間(回数)の設定が可能です。
これにより、事前に労働時間の把握が可能となるため、気が付いたら基準値を超える労働をしていたといったようなリスク回避に活用いただけます。
また、この設定は、事業所毎、雇用形態(雇用区分)毎に設定が可能ですので、複数の条件が必要となる企業様の管理にもお役立ていただけます。




