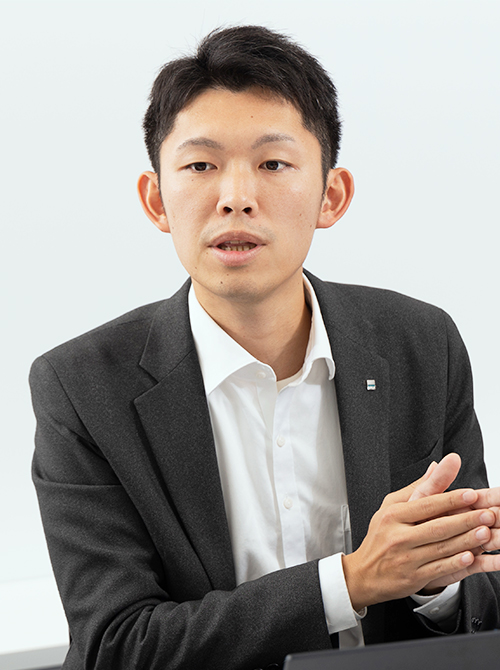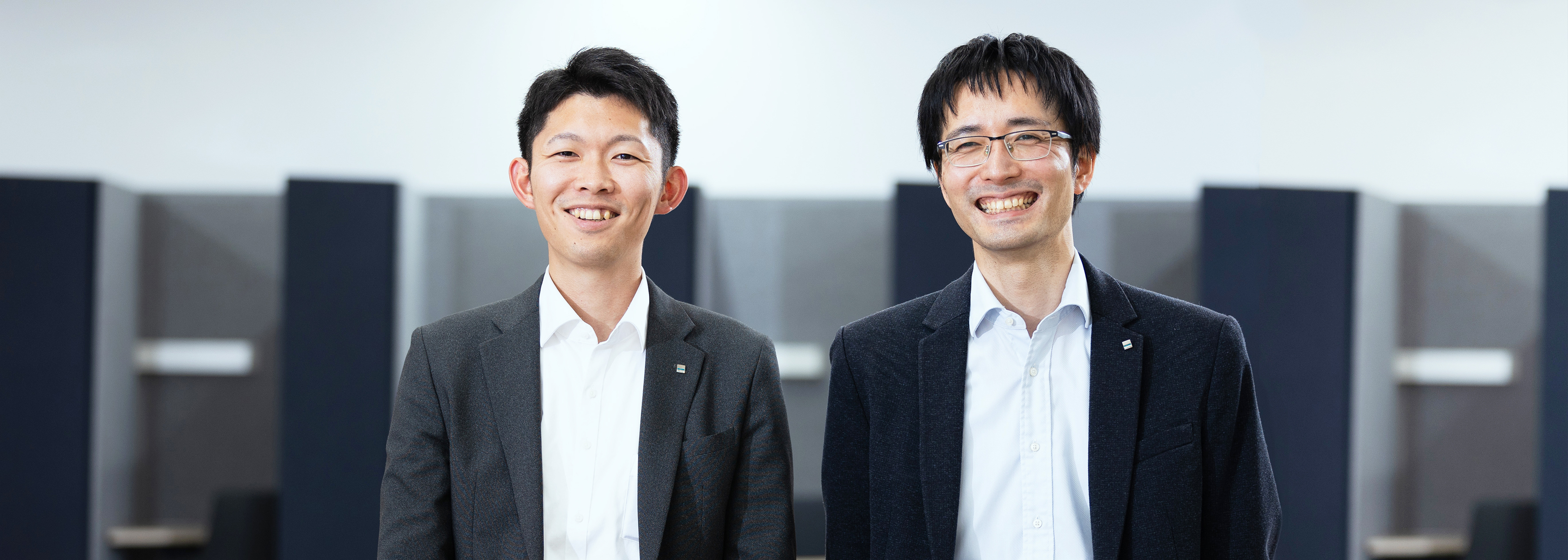どのようなハードルがありましたか。
N.T.
私の場合は「セコムIT未来像」プロジェクト発足から半年後に急きょメンバーとしてアサインされました。しかもプロジェクトマネージャー兼スマートフォン管理・設定チームのリーダーという重い立場です。ゼロトラストに関する知識がほとんどなく、しかもこの規模のプロジェクトをマネジメントした経験もない中での途中参画でしたから、プレッシャーは大きかったです。同時に、セコムグループのITインフラ刷新という今後二度とないかもしれないビッグプロジェクトに関われることに、胸が高鳴りました。
K.K.
プロジェクトメンバーは「あのN.T.さんが来てくれた!」と心強い思いでしたよ。特に私は以前一緒に仕事をさせていただいたときからN.T.さんの仕事ぶりをリスペクトしていたので、本当に嬉しかったです。
N.T.
プロジェクトの立ち上がりが2021年8月で、ゼロトラストの本番展開の予定が2022年12月。その間、PoCで指摘された技術的な課題をすべて解消させつつ、より理想的なIT環境に仕上げるために、何度も設計・テスト・考察を繰り返しました。それだけでなく、実際にセコム社員全員に新たな端末を配布しなくてはなりませんでした。
K.K.
端末と一言で言うけれど、膨大な数でしたね。
N.T.
1万台を超えていました。キッティング(各種設定)も手作業ではとても間に合わないので、リモートによって行われるゼロタッチのキッティングを採用しました。利用者がわかりやすいように、問い合わせの窓口やFAQも用意しました。また特定の部署が使用するアプリケーションが新しい端末では動かないことが判明したり、一定の条件下でゼロタッチキッティングが動かなくなったりしてその対応に追われるなど、さまざまなケースが発生しました。
K.K.
本番展開が近づく中、ギリギリの状態での作業が続きました。
N.T.
もし新しい端末が使えなかったら最悪のケースではグループ全体の業務が停止してしまいます。それは絶対に避けなければなりません。ですから見切り発車するわけにもいきませんでした。かといって本番展開を延期すれば、端末のライセンス料などで膨大なコスト増になってしまう。その中でプロジェクトマネージャーとして課題の一つひとつをトリアージ(優先順位の決定)し、決断を下さなくてはならないのが、私にとって大きなハードルでした。
K.K.
実はそんな大変な状況の中、私は子供が生まれたため育児休業を取っていたんです。その間、端末チームのリーダーとしての私の業務は、新卒で入社した若手に任せました。だから私は頭を抱えて悩むN.T.さんの姿は見ていないんです。代わりに育児にてんてこ舞いで頭を抱えていました。
N.T.
どのような状況でもしっかりと育児休業が取得でき、周囲もそれをサポートするのは、当社ならではの素晴らしい風土だと思いますよ。